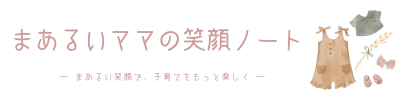「お宮参りって、いつやればいいの?」「生後何日目から数えるのか分からない…」——赤ちゃんの誕生後、初めて迎える大切な行事だからこそ、時期の決め方に悩むママパパはとても多いです。
伝統的には、生まれた日を1日目として数え、男の子は生後31日目、女の子は32日目にお参りするのが目安とされています。
でも実際には、ママや赤ちゃんの体調、季節、家族の都合に合わせて日程をずらすご家庭もたくさん。
無理のないタイミングで行うことが、何より大切です。
この記事では、お宮参りの日程を正しく計算する方法はもちろん、現代のライフスタイルに合った柔軟な考え方や、遅らせる場合の注意点までをわかりやすく解説します。
お宮参りはいつ?正しい計算方法を解説
「お宮参りって具体的にいつ行けばいいの?」と迷うママ・パパも多いですよね。
まず押さえておきたいのが、日数の数え方です。基本は、生まれた日を1日目として数えるのが一般的。
伝統的な目安では、
- 男の子:生後31日目
- 女の子:生後32日目
とされています。
例えば、4月1日生まれの男の子なら → 5月1日がお宮参りの目安という計算になります。
ただし、地域によっては「33日目」とするところもあり、考え方に違いがあるんです。
そのため、地元の神社や祖父母に確認してみると安心ですね。
自分で数えるのが不安なときは、お祝いの日付を自動計算してくれるサイトやアプリを使うのもおすすめです。
誕生日を入力するだけで目安日がわかるので便利です。
ここで大切なのは「絶対にこの日じゃなきゃダメ!」という決まりではなく、あくまで目安ということ。
赤ちゃんやママの体調、家族の予定に合わせて柔軟に日程を調整すれば大丈夫です。
お宮参りは「日にちより気持ち」。焦らず、家族みんなが笑顔で集まれる日に行うのが一番ですよ。
お宮参りはいつがいい?目安日と遅らせる場合
「1ヶ月ぴったりで行けなかったらどうしよう?」と心配になるママ・パパも多いですが、安心してください。
お宮参りは多少遅れてもまったく問題なしなんです。
実際には…
- 生後2〜3ヶ月にずらす家庭はとても多い
- 真夏や真冬を避けて、赤ちゃんが過ごしやすい季節を選ぶ
- 百日祝いとまとめて実施する家庭もある
- 半年後に落ち着いて行ったケースもある
このように、家庭ごとに柔軟にスケジュールを調整しているのが実情です。
つまり「1ヶ月を過ぎたらダメ」という決まりはなく、赤ちゃんやママの体調、家族の予定に合わせて無理なく行うことが一番大切。
お宮参りは「日にち」よりも「みんなが安心して参加できるか」がポイント!
家族にとってベストなタイミングを選んであげましょう。
お宮参りの計算方法とベストな日取り
「お宮参りって結局いつ行けばいいの?」——
これ、準備を始めると多くのご家庭がぶつかる疑問なんです。
まずは伝統的な計算方法を押さえて、そこからベストな日取りをどう決めるか考えていきましょう!
計算方法
お宮参りの日数は、生まれた日を1日目として数えるのが基本です。
- 男の子 → 生後31日目
- 女の子 → 生後32日目
たとえば、4月1日生まれの女の子なら → 5月2日 が目安日になります。
ただし地域によっては「33日目」とする風習もあるため、迷ったときは地元の神社や祖父母に確認しておくと安心です。
ベストな日取りを選ぶポイント
計算で出た日がそのままベスト、とは限りません!
大切なのは赤ちゃんと家族にとって無理のない日を選ぶこと。
- 赤ちゃんとママの体調が整っているか
- 気候(真夏や真冬を避けて過ごしやすい時期に調整する家庭も多いです)
- 六曜(「大安」を選ぶ人もいれば、まったく気にせず都合優先という人も増えています)
- 祖父母や家族の予定が合わせやすいかどうか
つまり、目安日はあくまで“参考”。
赤ちゃんの健康と家族みんなの笑顔を優先して決めた日こそ、最高のお宮参り日和になるんです。
お宮参りはいつ?計算方法からベストな日取りまで徹底解説まとめ
お宮参りの日程は、生まれた日を1日目として数えるのが基本。
男の子は31日目、女の子は32日目が伝統的な目安とされています(地域によっては33日目という場合もあります)。
ただし、「1ヶ月を過ぎたらダメ!」という決まりはありません。
実際には2〜3ヶ月ごろに行ったり、百日祝いと合わせて行ったりするご家庭も多いんです。
六曜や天気にこだわるより、まずは家族が安心して参加できる日を優先することが大切。
お宮参りの本来の意味は、形に縛られることではなく、赤ちゃんの健やかな成長を祈ること。
日程の計算はあくまで参考にしつつ、赤ちゃんと家族みんなが心から笑顔になれる日を選んでくださいね。